ブリッジズのトランジションのお話との繋がりで、今回はシュロスバーグを取り上げようと思いました。
変化の渦中にいると、自分の気持ちがつかみにくくなることがあります。
今回は、そんなときに役立つ「シュロスバーグのトランジション理論」をご紹介します。有名な4Sなど、キャリアについて考える時にツールとしても実用性抜群です。
トランジションには、どんなものがある?【3つの分類】
ナンシー・シュロスバーグ(Schlossberg,N.K. 1929-)は、転機(トランジション)を次の3つに分類しました。
■トランジションの3つ分類
1.予期された転機 :想定していたことが実際に「起こったこと」
例)結婚、退職、転職、親の介護など
2.予期されなかった転機 :予期していなかったことが「起きたこと」
例)失業、離婚、病気、災害、思いがけない昇進、転勤など
3.ノンイベント :想定していたことが、「起きなかったこと」
例)昇進しなかった、結婚しなかった、不妊など
人生には、転職、引っ越し、子育ての節目、家族構成の変化など、想像していたことが予定通り起こるようなイベントがありますね。これが1つ目の「予期された転機」です。
これは比較的心の準備ができ、みなさん意識しやすいことと思います。
また、災害や思いがけない転勤など「思っていなかったことが起きた」ということが、2つ目の「予期されなかった転機」です。想定していない分、動揺が大きいことが多いかと思いますが、事象としては分かりやすい内容かと思います。
一方で、3つ目の「ノンイベント」は、「振り返ってみればそうだった」ということも多く、気づきづらいことも多いのではないでしょうか?例えば、35歳には昇進して管理職になると何となく漠然と思い描いていたけれど、その年齢になってみて実際はまだしていない。これも場合によっては、転機だということです。
もっと言えば、36歳で昇進したら「大体35歳ごろに昇進したから転機には該当しなくなる」かもしれないし、「36歳までに昇進しないとダメだと強く思っていれば、転機になる」かもしれない。
そう考えるとこのノンイベントという考え方、新鮮な視点ではないでしょうか?
私は「転機って、主観的なものなんだな」と強く実感したことを覚えています。
転機を予測する/しないはその人による。
タイミングや外部要因などの兼ね合いもあり、起きたり/起きなかったりする。
その人の考え方により、起きたことになったり/起きなかったことになったりということも有り得るということ。味わい深いですね。
だからこそ、変化そのものの内容だけでなく、「自分がどう感じたか」「どう準備できたか」がその後の適応にも大きく関わるのです。
出来事の良い・悪いも、社会的に一般にそう思われているということはあまり関係ないんじゃないかなと思います。例えば、結婚と聞くとおめでたいことと判断しがちですが、そのためにキャリアにマイナスの影響がある場合などはかなり負荷の高いトランジションということになるでしょう。
あくまで「それぞれの人にとってどんな意味を持つのか」が大事だなと思います。
では、シュロスバーグは、こうした人生の転機(トランジション)にどう向き合うことを提唱したのでしょうか?ツールとしても具体的でかなり実用的な考え方を教えてくれていますよ。
4Sってなに?変化を乗りこえる【4つの視点】
トランジションに気づいたとき、私たちは何に支えてもらい、どう乗りこえていけばいいのか?
このヒントとして、この「4S」というフレームが提案されています。
これは、普段キャリアにちょっと迷った時にも活用しやすいので、存在を知ってもらえると嬉しいです。
ちなみに私はこの4Sの概念を知ったとき、メーカー勤務だったこともあり5Sの仲間かな?と思いました(全然違いました)。
■4Sとは
1.Situation(状況)
どんな変化が起きたのか? その変化は自分で選んだものか、突然だったのか。
2.Self(自己)
自分はどんな性格・価値観を持っているか? これまでどうやって困難を乗り越えてきたか。
3.Support(支援)
周囲に相談できる人はいるか? 家族や友人、職場などの支えはあるか。
4.Strategies(戦略)
変化にどう対処しているか?
視点を変える、行動する、気持ちを整えるなどの工夫はできているか。
この4つの視点から自分の状況を見つめ直すことで、「今の自分は、何に支えられ、何に戸惑っているのか?」が少しずつ見えてきます。
変化が起きると、無理に前向きに捉えようとしたりしがちですが、このフレームワークに沿って考えると現在位置を知ることができます。そこから、自分のリズムで、少しずつ動いていけばいいと思うと、安心できますよ。
私は特に、この概念を知る前は、Supportの概念がすっぽり抜けていました。「全部自分でやるのが当たり前」と思いがちだったのですね。でも、周りで相談できる人や、公的機関、本なんかも含め、支えてもらえることがたくさんあることに気がついていきました。
このあたりのヒントも、また別の機会に書いていきたいと思います。
どうトランジションに対処していく?【3ステップ】
変化に戸惑うとき、「何から手をつければいいのか分からない」と思うことはありませんか?
シュロスバーグの理論では、そうした「変化の中にいる自分」を静かに見つめ、いざトランジションが起きた際に役立つ。以下のような対処法の手順も示されています。
① まずは「変化に気づく」
たとえば、退職、転職、引っ越しなどの「はっきりとした変化」だけでなく、
「本当はやりたかったことができなかった」「期待していた未来が来なかった」といったノンイベントの静かな変化も、私たちの心に影響を与えています。
→これらに気がづくのが第一段階です。
気がつくためには、数年おきなどに定期的に振り返ってみるのもおすすめです。
② 次に「4Sで状況を整理する」
変化を乗り越える力は、個人の強さだけで決まるものではありません。
先ほどご紹介した、4Sを使って、自分の状況を見つめ直していきます。
→4Sは様々な観点から今の自分を丁寧に見つめることで、少しずつ霧が晴れてくるようなフレームワークです。自分を総合的に見つめられるようになっていけます。
③ 「小さな行動」へつなげる
4Sをもとに「いまの自分の状況」を把握できたら、無理のない範囲で、できることを探してみましょう。
・誰かに話してみる(Supportを動かす)
・自分にやさしい言葉をかける(Selfへのケア)
・小さなタスクから取りかかってみる(Strategiesを広げる)
・今の状況を紙に書き出す(Situationを客観視) などなど
→行動はスモールステップで、小さくてOKです。
「この変化の中で、自分にできることはある」と感じられることが、前に進むきっかけになります。
どうでしょうか?こうして具体的なステップがあると、心強いですよね。
様々な資源を活用し、自分を支えていくためのヒントをくれています。
まとめ・メッセージ
ここまで、シュロスバーグの理論について、「トランジションの3つの分類」「4Sのフレームワーク」「トランジションへの対処(3ステップ)」を解説しました。いかがでしたか?
人生のトランジションは、時に不安で、静かで、そしてとても個人的なものです。
だからこそ、理論をヒントに、自分に合ったペースで向き合っていけたらいいですね。
私は過去のトランジションをいくつか振り返って4Sに沿って整理するワークをおすすめしています。これによって、自分の使いやすい資源や、他に活用できる可能性がある資源が見えてきます。みなさんも良かったらやってみてくださいね。
変化に向き合う力は、「自分を理解する視点」から育っていくと私は思っています。そして必要なときに、4Sのフレームをそっと思い出していただけたら嬉しいです。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
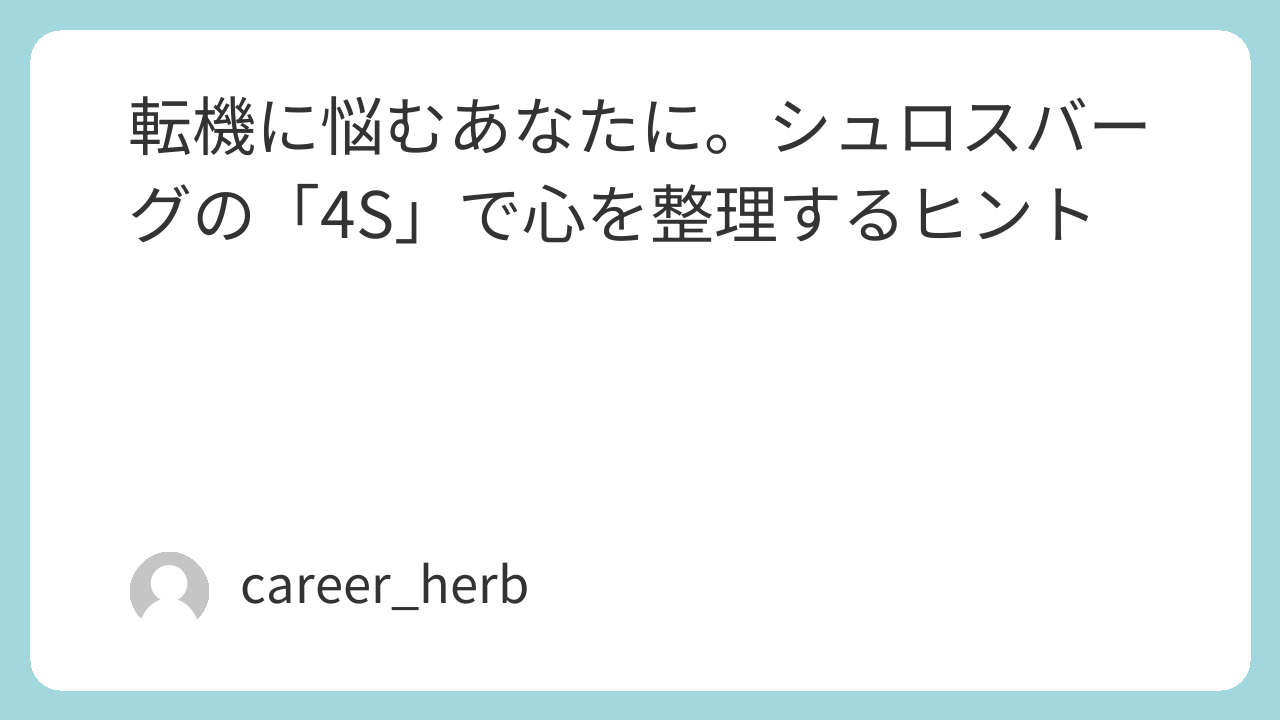

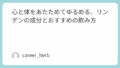
コメント